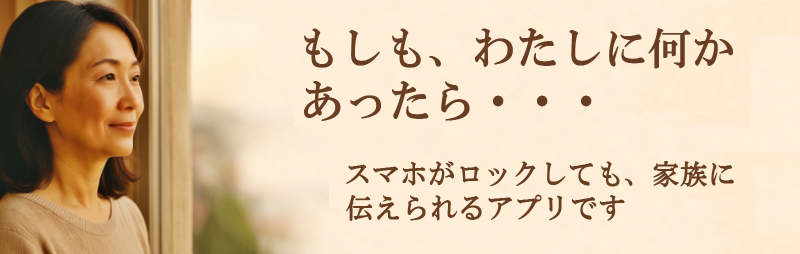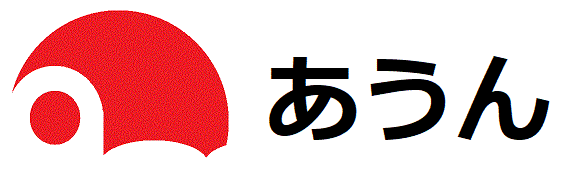死んだ後にメールを届けるという選択肢|デジタル遺品と新しい終活の形

私たちの生活は、スマートフォンやパソコンを通じて完全にデジタル化しています。
銀行口座、保険契約、サブスク、SNS、写真や動画の保存先まで、その大部分が「デジタル資産」として存在しています。
こうした資産が死んだ後にどうなるのか──近年、デジタル遺品問題が深刻さを増していることをご存じでしょうか。
デジタル遺品問題が増えている理由

従来の遺品整理と違い、デジタル遺品は目に見えません。
家族が知らないまま眠っている口座や契約、あるいは個人的なやり取りが残されたままになるケースも少なくありません。
こうしたトラブルを防ぐために、国民生活センターも「パスワード等を生前に共有すること」を推奨しています。
実際に、パスワードを遺族に伝えておくことで、解約や相続がスムーズに進む事例もあります。
しかし一方で、「生前にすべてのパスワードを家族に渡すのは抵抗がある」という声も多いのが現実です。
個人的なメールや日記、SNSの内容を生きている間に見られたくない人もいますし、最後までプライバシーを守りたいと考える人も少なくありません。
死んだ後にメールで伝えるアプリ

そこで登場したのが、死んだ後にメールで大切な人へメッセージを届けるアプリです。
生前に登録しておけば、自分が亡くなった後、事前に指定した宛先にメールが送信される仕組みです。
このようなアプリには次のような利点があります。
- 生前は伝えづらかった思いを、死後に伝えられる
- パスワードや契約情報など、必要最低限の情報だけを届けられる
- 家族や友人への「感謝の言葉」を残せる
- 書面や口頭では難しい「時期を選んだ伝言」が可能
プライバシーを守りつつ、大切な人へメッセージを残すことができる点が、多くの利用者から支持されています。
ただし、メールには限界がある
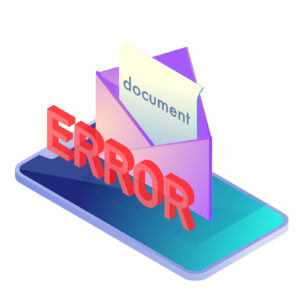
便利な仕組みではあるものの、死んだ後にメールが確実に届くかというと、そこには限界があります。
具体的には次のような問題が起こり得ます。
- 受取側のメールサーバーやメーラーの設定により、迷惑メールに振り分けられる可能性
- 迷惑メールから除外設定をしていても、OSやメーラーのバージョンアップで設定がリセットされることがある
- アプリから送信されたメールは特に迷惑メール判定を受けやすい
- 受取者が後にメールアドレスを変更してしまう可能性
つまり、死んだ後に送るメールが相手に届かないという重大なリスクが存在するのです。
これは、単なる不便ではなく、人生の最期に残した大切なメッセージが届かないという大きな問題です。
そうした問題が発生しないように、現在、オペレーターが介入して、死後、確実に大事を家族に届けてくれるサービスもあります。
自動送信と人のサポート、どちらを選ぶか
「重要なメールが今まで届かなかったことはないから、自動送信で十分だ」と考える人もいるでしょう。
それはそれで正しい選択です。
自動送信の手軽さを選ぶか、人のサポートによる確実性を重視するか──選択は自由です。
どちらにせよ、死んだ後にメッセージを届ける仕組みは、今のデジタル社会において確実に必要なものといえるでしょう。
まとめ
死んだ後の自分を想像するのは簡単ではありません。
しかし、大切な人に伝えたい想いや情報があるならば、今のうちに準備しておくことが大切です。
自分にあった方法で、大事をわたすことが自分にとっても家族にとっても、よりよい未来につながるのです。