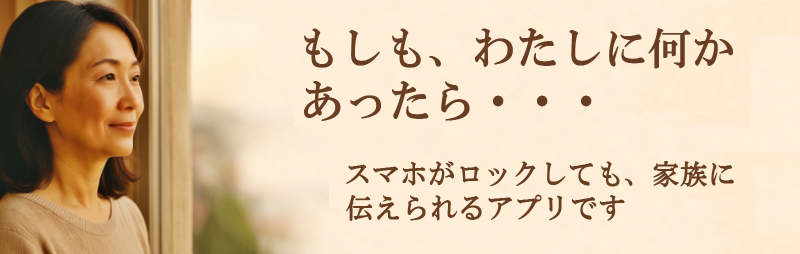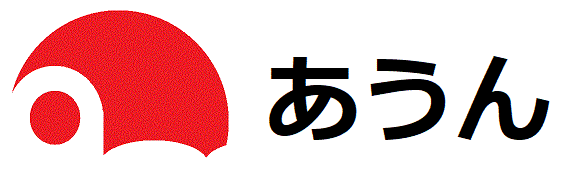デジタル遺品、どうする? 発展の陰に残る「見えない遺品」への備え

技術や便利さの進歩は生活を豊かにしますが、同時に思わぬ負の側面を生みます。
たとえば自動車が急速に普及した時代には交通事故の死者数が激増し「交通戦争」と呼ばれた歴史がありました。
こうした「発展の光と影」はテクノロジーにも当てはまります。
スマートフォンやクラウドに残るデータや契約――いわゆる「デジタル遺品」は、見えにくく整理されていないことで、残された家族に大きな負担やトラブルをもたらします。
1 デジタル遺品とは?

「デジタル遺品」とは、故人が残したスマホやPCの中の写真・メッセージ、SNSやクラウド上のアカウント、ネット契約(サブスク・ネット銀行・電子マネー・仮想通貨など)といった、物理的ではないデータやオンライン上の権利・契約を指します。
明確な法的定義はまだ整っていないため、扱いはサービスや契約ごとに異なります。
特徴としては:
- 目に見えにくく(クラウドや暗号化されたデータなど)、所在が分かりにくい
- 端末やサービスが複数に分散していることが多い
- パスワードや規約で遺族が容易にアクセスできない場合がある
2 被害が大きいスマホ

なかでもスマホは“個人情報のハブ”であり、最も被害が大きくなりやすい媒体です。
理由は次のとおりです。
- 個人情報が集中:電話帳・メッセージ・写真・位置情報・各種ログイン情報などが一台に集約されている。
- ロックや生体認証で中身が見られない:PINや指紋・顔認証が設定されていると、遺族でも解除できないことが多い。
- 自動課金が続く:サブスクリプションやアプリ課金が解約されず請求が続くケースがある。
- 金融・資産に直結:ネット銀行や電子マネー、仮想通貨の情報がスマホにあり、アクセスできないと資産管理が滞る。
- 思い出が失われるリスク:写真・動画が端末内だけでバックアップがないと取り出せないままになる。
実際に国民生活センターにも「スマホのパスワードで口座や契約が確認できない」「サブスクの請求が止まらない」といった相談が寄せられており、金銭的・精神的な被害につながっています。
3 デジタル遺品のトラブルを防ぐにはどうする?

デジタル遺品のトラブルを減らすため、日ごろからできる準備があります。
- 利用サービス一覧を作る:SNS、メール、クラウド、ネット銀行、サブスクなどを一覧にして、ログイン方法の手がかりを記す。
- 重要データのバックアップ:写真・動画・重要書類は必ずバックアップをしておく。
- ログイン情報の安全な保管:紙で残す場合は耐火金庫など安全な場所に。パスワードマネージャーを使うなら、どのように相続者にわたすかを決めておく。
- 家族への連絡:利用するサービスなどの情報を家族に伝えておく。
- エンディングノートの活用:希望や手続きをエンディングノートに記すことで、遺族の負担が減る。
まとめ
デジタル遺品は「形が見えない」「所在が分かりにくい」「規約で扱いが限られる」点が、遺族の負担やトラブルを大きくします。
日常のうちから利用サービスの一覧化、バックアップ、ログイン情報の安全な管理、信頼できる引継ぎ先の明示などを行えば、もしものときの迅速な対応につながります。
まずは「どこに何があるか」を整理することから始めましょう。