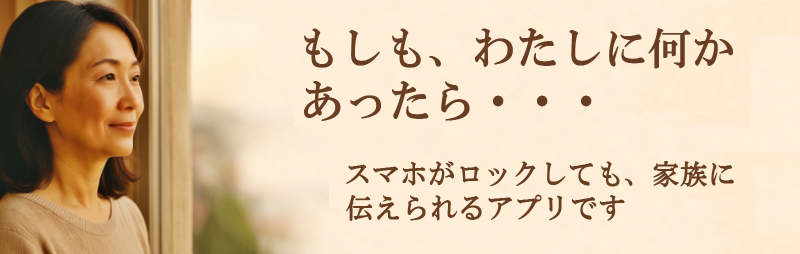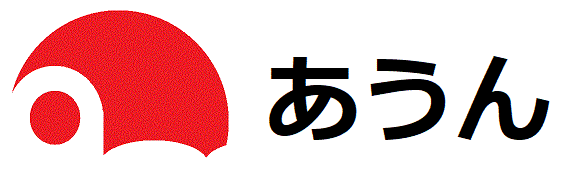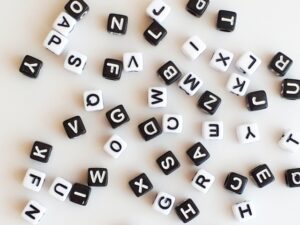公正証書遺言の作り方と注意点|安心できる相続準備

相続の場面では、残された家族のあいだで思いがけないトラブルが起こることがあります。
特に相続人が複数いる場合、財産の分け方について意見が食い違い、家族関係がぎくしゃくしてしまうことも少なくありません。
そうした事態を防ぐために有効とされているのが、公正証書による遺言です。
1. なぜ公正証書遺言を利用するのか
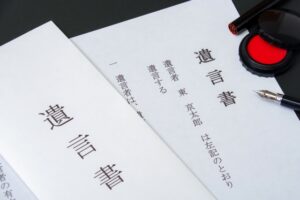
遺言には大きく分けて以下の3種類があります。
- 自筆証書遺言:自分で全文を書き、署名押印する形式。費用はかからず簡単ですが、形式の不備で無効になることがあるほか、発見されないまま放置されるリスクがあります。
- 秘密証書遺言:遺言の内容を秘密にしたまま、公証役場で遺言を預かってもらう形式。利用は少なく、実務的にはあまり使われません。
- 公正証書遺言:公証人が作成し、公証役場に原本が保管される形式。法的にもっとも確実で、紛失や改ざんの心配がありません。
相続人が複数いて意見が割れそうな場合や、不動産など分割が難しい財産がある場合には、公正証書遺言を作成しておくことが、トラブルを防ぐ予防策になります。
2. 公正証書遺言の作り方

実際に公正証書遺言を作る流れは次のようになります。
- 必要書類の準備
・遺言者の印鑑証明書や戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書
・預貯金の残高証明や通帳の写し など - 公証人への事前相談
公証役場に事前に連絡し、財産の内容や希望する分け方を伝えます。弁護士や司法書士に依頼して内容を整理してもらう方も多いです。 - 証人の手配
公正証書遺言には証人2名が必要です。親族や相続人は証人になれないため、専門家に依頼するのが一般的です。 - 公証役場で作成
公証人が遺言内容を確認し、口述をもとに文書を作成します。署名・押印が済めば、その場で公正証書遺言が完成します。 - 公証役場で保管
正本と謄本が遺言者に交付され、原本は公証役場で保管されます。紛失や改ざんの心配がない点が大きな安心材料です。
3. 公正証書遺言で気を付けたいこと

公正証書遺言は法的に強力な効力を持ちますが、いくつか注意点があります。
- 費用がかかる:遺産の金額に応じて手数料が発生します。数万円から数十万円になることもあるため、事前に確認が必要です。
- 証人が必要:証人の人選に迷う場合、専門家に依頼するとスムーズです。
- 内容の見直し:財産状況や家族構成が変われば、遺言の内容を見直す必要があります。
- 遺言の存在を家族に伝えること:公正証書遺言は公証役場に保管されますが、家族が遺言の存在を知らなければ請求されず、実際に開示されない可能性があります。生前に「遺言を作成してある」とだけでも伝えておくことが重要です。
4. 遺言で生前にもめたくない人は・・・
複数の相続人がいる場合、相続分に敏感な人もいます。
そのため、内容を知りたがったり、家族関係がおかしくなったりすることもあり、遺言の存在を切り出しにくい場合もあります。
そうした人はどうすればよいでしょうか?
当社の終活アプリ「ロックの向こう」は、利用者の安否が一定期間確認できなくなると、大切な情報を指定した相手に届けてくれる仕組みです。
オペレーターのサポートのもとで、家族は大切な情報を受け取ることもできます。

このアプリに弁護士の連絡先などを登録しておけば、生前に家族に説明する必要がありません。
また、遺言書に書けないような内容を一緒に書いておくこともできます。
まとめ
相続をめぐるトラブルは、家族にとって大きな負担になります。
その予防策として、公正証書遺言を作成しておくことは大きな安心につながります。
さらに、新しい仕組みを活用すれば、遺言書だけでは補えない部分もサポートできます。
大切な人への思いやりを形にするために、早めの準備を心がけることが大切です。