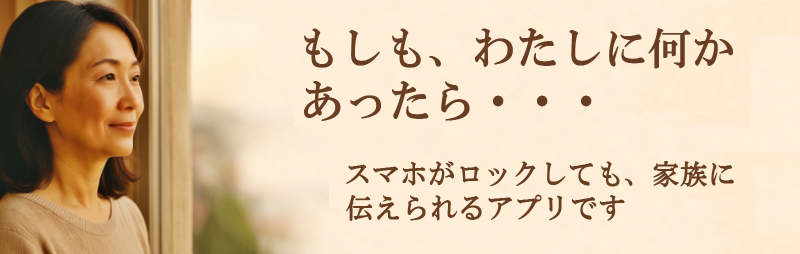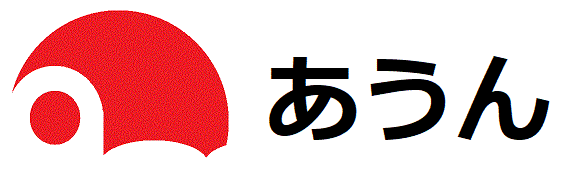デジタル遺品サービスの種類と特徴|メリット・デメリットを徹底解説
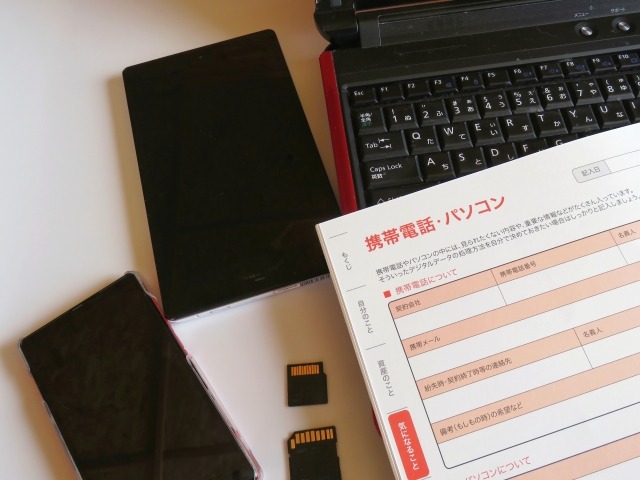
目次
近年「デジタル遺品」という言葉を耳にする機会が増えてきました。
スマートフォンやパソコンを持つことが当たり前になった今、誰もが自分の死後に残される「デジタルデータ」を抱えています。
写真やメール、SNSアカウント、ネット銀行や証券口座、マイナンバーカードなど――デジタルデータは私たちの生活に深く結びついています。
こうした背景から、デジタルデータ=デジタル遺品を整理・管理するための「サービス」も年々増加しています。
この記事では、デジタル遺品の種類や代表的なサービスの内容を整理し、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
1. デジタル遺品とは?

「デジタル遺品」とは、亡くなった人が生前に利用していたデジタルデータやアカウントの総称です。
代表的なものには以下があります。
- スマホやパソコン内のデータ:写真、動画、連絡先、メモ、アプリの情報など
- インターネット上のアカウント:SNS(Facebook、Instagram、Xなど)、メールアドレス、オンラインショップ会員情報
- 金融関連のデータ:ネットバンキング、証券口座、仮想通貨ウォレットなど
- クラウドサービス:Google Drive、iCloud、Dropbox などに保存されたデータ
中でも普及率の高さから、最も重要なデジタル遺品は「スマホ」といっても過言ではありません。
日常のほとんどがスマホに集約されているからです。
2. デジタル遺品のトラブルとは?

デジタル遺品は便利である一方、死後の管理が不十分だと家族や遺族に大きな負担を与えます。
実際によく起こるトラブルを見てみましょう。
よくあるトラブル事例
- スマホのロック解除ができない
パスコードがわからず、写真や連絡先、銀行アプリなどにアクセスできない - ネット銀行・証券口座にアクセスできない
通帳がなく、ログイン情報も不明のため、利用先がわからずに相続手続きができない - SNSアカウントが放置される
FacebookやInstagramなどがそのまま残り、亡くなったことを知らない人からメッセージが届いたり、乗っ取りの被害に遭ったりする - サブスクリプション契約の継続
音楽配信や動画サービス、クラウドサービスの月額利用料が解約されず、引き落としが続く - クラウドストレージのデータ消失
銀行口座の凍結やクレジットカード解約で料金未払いとなり、アカウントが停止。大切なデータが削除される - 仮想通貨や電子マネーの消失
秘密鍵やパスワードが不明で、資産として相続できないまま失われる
これらはスマホの中に「本人しか知らない情報」が多いために発生します。
従来の遺品整理では通帳や紙の契約書を探せば解決できましたが、デジタル遺品は「アカウント情報」「パスワード」「端末ロック解除情報」がそろわなければ、資産も思い出も失われてしまうリスクが高いのです。
3. デジタル遺品のサービスとメリット・デメリット
デジタル遺品に対応するサービスには、いくつかの種類があります。
ここでは代表的なものを紹介し、それぞれの特徴やメリット・デメリットを見ていきます。
(1)デジタル遺品整理業者
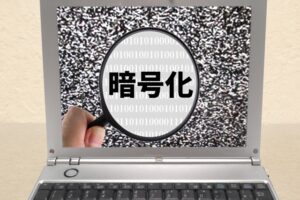
専門業者が遺族の代わりにスマホやパソコンを解析し、写真・文書・金融情報などを抽出するサービス
メリット:事前の準備が不要で、必要になった時点で依頼できる
デメリット:セキュリティが強固な端末(例:iPhone)は解析できない場合もある。費用は数万円~数十万円と高額で、成功報酬制でないため結果が得られなくても費用が発生する
(2)オンラインアカウント管理サービス(Google・Appleなど)
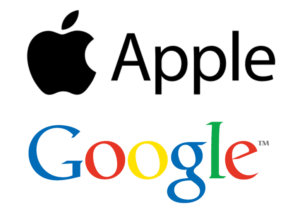
Googleの「非アクティブアカウントマネージャー」やAppleの「デジタル遺産プログラム」など。生前に信頼できる人を登録しておき、死後にアカウントの管理や削除を委任できる仕組み。
メリット:無料で利用可能。主要なサービスに標準搭載されている
デメリット:Appleはアクセスキーと死亡証明書の提出を共有者自身がしなくてはならず、手続きが煩雑。Googleは比較的簡単だが、最終ログインから最短3か月後にしか適用されない
(3)エンディングノート
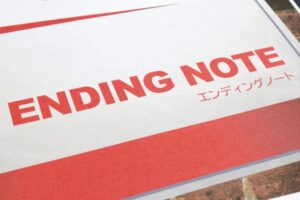
紙のノートやスマホアプリを利用し、パスワード・契約状況・伝えたいメッセージなどを記録する方法。
メリット:テンプレートが無料公開されており、費用をかけずに始められる
デメリット:生前に第三者に見られてしまうリスクがある
(4)遺品データ保存サービス(クラウド保存)

クラウドストレージに写真や文書を保存し、家族が共有できるようにするサービス。
メリット:大切な思い出を長期保存でき、家族で共有しやすい
デメリット:死後に口座凍結やカード解約があると料金未払いとなり、データが削除されるリスクがある
(5)自動削除・自動消去サービス

一定期間ログインがなければ、自動的にデータを削除する仕組み。
メリット:見られたくない情報を家族に残さずに済む
デメリット:誤作動や設定ミスにより、残したいデータまで消えたり、逆に消去されないリスクがある。
(6)当社サービス「ロックの向こう」
重要なログイン情報やデータを安全に保管し、利用者の死後に遺族へ確実に届けるサービス。
メリット:死後に必要な情報を、オペレーターのサポートの元、家族が安全に受け取れる。データは分割保存されるため、漏洩リスクがない
デメリット:サブスクリプション契約が必要

まとめ
デジタル遺品は、現代を生きる誰にとっても避けられないテーマです。
スマホやパソコンに詰まった膨大なデータは、資産や思い出として価値がある一方、管理を誤れば大きなトラブルを招きます。
そのため「デジタル遺品サービス」を上手に活用することが大切です。
業者依頼、オンラインサービス、エンディングノート、クラウド保存など、それぞれに一長一短があります。
自分に合った方法を選び、生前から備えておくことで、家族の負担を軽減し、安心してデジタル時代を生きていけるでしょう。