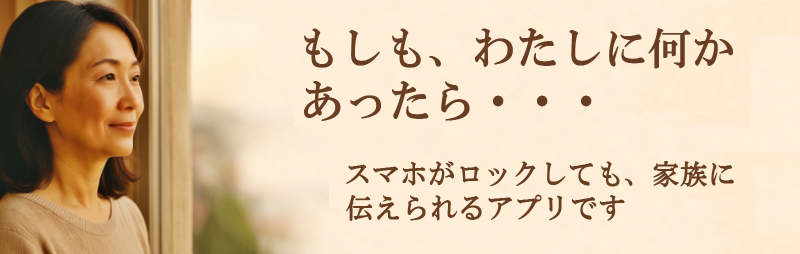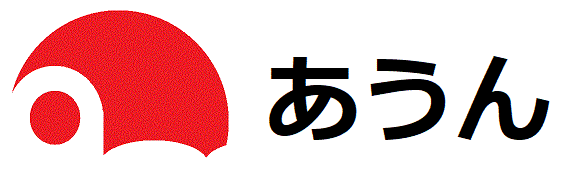デジタル資産と遺言|スマホ時代に考える新しい終活

今の時代、私たちの生活の大切な一部はスマホやパソコンの中にあります。
銀行のインターネット口座、電子マネー、ポイントサービス、SNSのアカウントや写真、動画…。
これらは「デジタル資産」と呼ばれ、目に見えなくても確かに存在し、金銭的な価値を持つものもあります。
私たちは日常生活でプライベートでも仕事でもスマホを使っています。
そのため死後、家族がスマホにアクセスできないことを考えると、パスワードを含めて遺言を残しておくことは、デジタル資産を守るひとつの手段といわれています。
本記事では、デジタル資産を残すために「遺言」をどう活用できるのかを、わかりやすく解説していきます。
1 スマホロックによる被害と原因

大切な家族が亡くなったあと、残されたスマホのロックが解除できず、写真や連絡先、金融情報が確認できないという事例は多くあります。
ロック解除ができなければ、銀行や証券口座にアクセスできず、資産の存在自体が家族に伝わらないまま失われてしまうことも。
原因は、本人しか知らないパスコードやID・パスワードが適切に共有されていないためです。
セキュリティを重視するあまり、家族にさえ教えていなかったことが、逆にトラブルを生んでしまうのです。
3 遺言でデジタル資産を残す
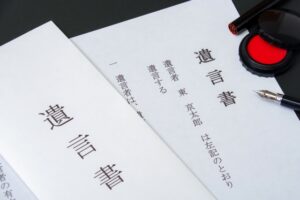
こうしたトラブルを防ぐ方法のひとつが「遺言」を利用して、スマホのパスコードや重要なアカウント情報を伝えることです。
遺言には資産の分け方だけでなく、「デジタル資産の存在を家族に知らせる」という役割も持たせることができます。
たとえば「私のスマホの暗証番号は〇〇で、ネット銀行の口座は△△銀行にあります」と明記しておけば、残された家族はスムーズに手続きを進めることができます。
4 遺言を作成するのは簡単
遺言にはいくつかの種類がありますが、もっとも身近でよく使われるのが「自筆証書遺言」です。
紙とペンがあれば作成でき、費用もかかりません。
ただし、自筆証書遺言には法的拘束力が弱いという注意点があります。
法的な効力を確実にしたい場合は、弁護士や司法書士、公証人に依頼して「公正証書遺言」を作成する必要があります。

5 遺言書は預かってもらった方がよい?

作成した遺言をどこに保管するかは非常に重要です。
自宅で保管することもできますが、その場合は「生前に見られてしまうリスク」や「隠しすぎて見つけてもらえないリスク」があります。
外部で預けることで、そうした心配は減らせます。
- 自筆証書遺言 → 法務局の保管制度を利用可能
- 公正証書遺言 → 公証役場で保管可能
ただし、どこに預けたとしても、家族(相続人)からの連絡がなければ開示されません。
家族が遺言の存在が知られなければ、放置される可能性もあります。
そのため、外部に預ける場合は必ず「どこに預けたか」を家族に伝えておくことが必要です。
6 家族が知らなくても死後連絡をくれるサービスは?

- 「保管先の名前と連絡先を紛失してしまわないだろうか」
- 「法務局へ預けたことを忘れてしまわないだろうか」
この先、長い年月を考えると十分ありえることです。
この問題を解決できるのが、死後に家族へ連絡を届ける仕組みを備えたアプリ「ロックの向こう」です。
このアプリは、安否確認がとれなくなると、伝えたいメッセージや情報を家族に届けることができます。
「生前に見られる不安」と「死後に伝わらない不安」の両方を解消できる、新しい終活の形といえるでしょう。
公正証書遺言を使う必要がある場合でも、「ロックの向こう」と併用すれば、保管先を家族に確実に伝えることが可能です。
まとめ
デジタル資産は、今や誰にとっても大切な財産の一部です。
しかし、スマホのロックやパスワードが原因で家族に伝わらないまま失われてしまうケースは少なくありません。
その対策として「遺言」を活用することも一つの方法です。
遺言を作成し、信頼できる場所に預け、家族に存在を知らせておくこと。
さらに安心を求めるなら「ロックの向こう」のような仕組みを利用すること。
これらを実践することで、自分も家族も安心できる未来につながります。