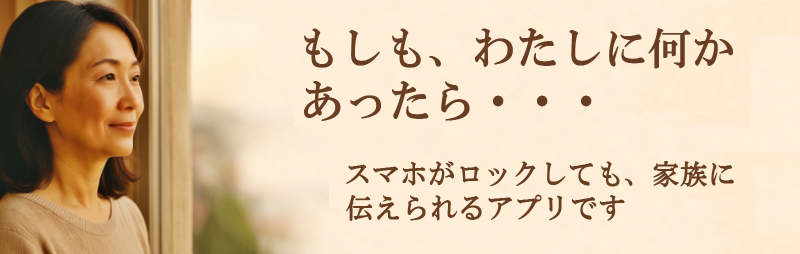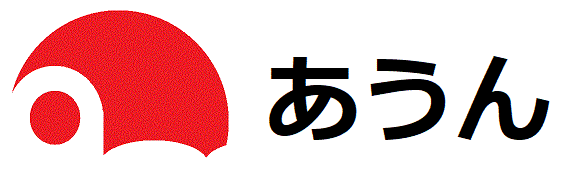社会人の子どもを心配してよい3つの理由
〜親ができる“支え”とは〜
「子どもが社会人になれば、もう心配はいらない」

そう思っていたはずなのに、なぜか不安が消えない。
そんな気持ちを抱えていませんか?
実はそれ、あなただけではありません。
多くの親が、社会人となった子どもの将来について"心配"しています。
それが決して過保護とは言い切れない、3つの理由を紹介します。
目次
1. 社会人になっても安定とは限らない

厚生労働省の最新調査(2024年)によると、正社員ではない“非正規雇用”の割合は、以下のように高い水準にあります。
(出典:厚生労働省「労働力調査」2024年)
- 20代の就業者:約22.9%
- 30代の就業者:約33.8%
- 40代の就業者:約24.6%
つまり、年齢が上がっても、安定した職に就けていない人が多くいるという現実があります。
さらに、収入面でもその厳しさは明確です(非正規を含む平均年収)
- 20代:約122万円
- 30代:約306万円
- 40代:約530万円
20代は自立するには難しい金額です。
「社会人=安定」というイメージは、もはや過去のものなのです。
2. 支出増と生活費のプレッシャー
たとえ正社員であっても、若者にとって、日々の生活は決して楽ではありません。
総務省の家計調査によれば、独身の生活費は月に16万~19万円が平均。
一見すると収入の範囲内に見えても、急な出費や病気などに備える余裕は乏しいのが現実です。
さらに、結婚して家庭を持つと、支出は一気に増えます。
親子3人(夫婦+子1人)の生活費:年間370万~400万円
生活基盤が不安定な中で家族を持てば、それだけ金銭的リスクも増えていきます。

3. メンタル不調と社会的孤立のリスク
働く若者たちが直面する精神的なストレスや不安も見逃せません。
厚生労働省の報告によれば、うつ病や適応障害の患者数は20・30代で増加傾向にあります。
新卒で就職した人の約30%が、就職後3年以内に離職しています。
(出典:厚労省「新規学卒就職者の離職状況」)
職場の人間関係、成果主義のプレッシャー、SNSによる劣等感など、現代社会の若者は多くの心理的負荷を抱えています。

子どもが大人になっても、親の支えは必要
子どもは自立し、自分の道を歩んでいきます。
親としては「干渉せずに見守る」姿勢が基本かもしれません。
けれども、人生には思いがけない出来事がつきものです。
そんなとき、心理的にも経済的にも親の支えが必要になるでしょう。
副業で生まれる“こころと暮らしのゆとり”
子どもが社会人になり、学費の支払いが終わっても、老後資金の確保で、自分自身の家計にも余裕がないという方も多いでしょう。
そんな方にこそ、おすすめなのが「副業」です。
月に数千円~数万円、備えの資金として大きな意味を持ちます。
さらに、自分自身のやりがいになるかもしれません。

まとめ:いざという時の“準備”を、今から
- 非正規雇用や収入の不安定さ
- 増え続ける生活コスト
- ストレス社会によるメンタル不調
これらは、社会人になった子どもを持つ親が“心配”して当然の課題です。
その“心配”を行動に移して経済的・精神的なゆとりにすれば、子どもの支えにもなります。
当社では、そんな「いざという時」のために備えるサービスを提供しています。
わずかな副業収入の一部を、有意義に使える仕組みをご用意しています。
興味がある方は、下記のバナーからご覧ください。